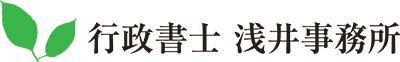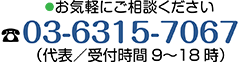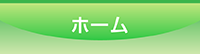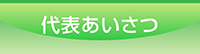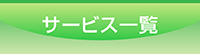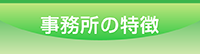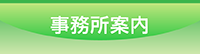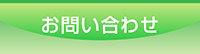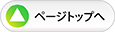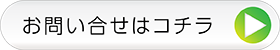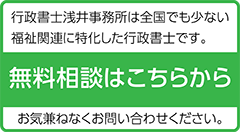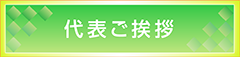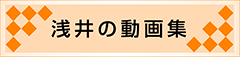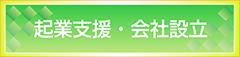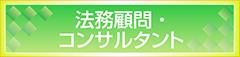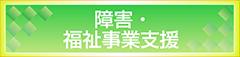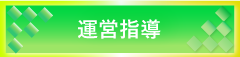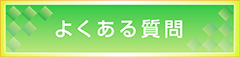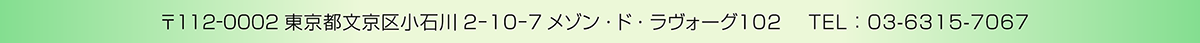■共同生活援助事業における食費の利用者負担について
こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は共同生活援助事業における食費の利用者負担についてお伝えします。
1. 利用者負担の原則
(1)事業者が、指定共同生活援助を提供する利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限られています。
(基準省令第213条、第213条の11、第213条の22)(条例第197条、第197条の11、第208条)
(2) 指定共同生活援助の提供をした際は、利用者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額(原則1割負担)の支払を受けるものとしているほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を利用者から受けることができるとされています。
(基準省令210条の4、第213条、第213条の11)(条例第187条、197条の11、208条)
1 食材料費
2 家賃
3 光熱水費
4 日用品費
5 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの(以下「その他の日常生活費」という。)
※上記1~5を徴収する場合は、あらかじめ利用者に対してサービスの内容及び費用について説明し、同意を得てください。費用を徴収した場合は、利用者に対して領収証を交付してください。
(3)指定共同生活援助において提供される「便宜に要する費用」とは、実費相当額に当たることから、その積算根拠を明確にし、適切な額を定めるとともに、定期的に精算する必要があります。
2. 食費の取り扱い
食材や調味料等の購入代金のみを根拠として金額を設定してください。
定期的に精算し、余剰金が生じた場合は、他の費目に充当するのではなく、利用者に返金してください。
上記のように、令和4年6月の福島市健康福祉部福祉監査課様の資料では記載があります。
こちらは指定権者によって取り扱いが異なると思いますので、必ず指定権者の意向を確認して頂くようお願いします。
また、利用者負担を行う際は、上記の通り利用者負担は実費相当額であること、利用者から同意を得ること、領収書を交付すること、定期的に精算することは、必ず行うようにしましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。
共同生活援助事業における食費の利用者負担について