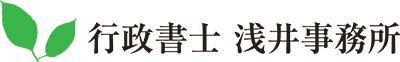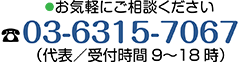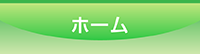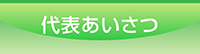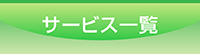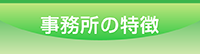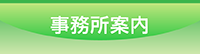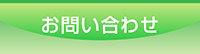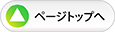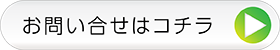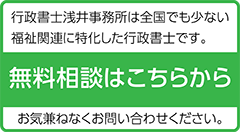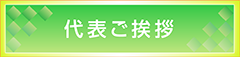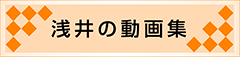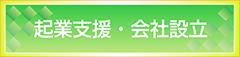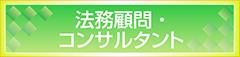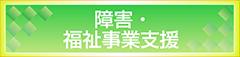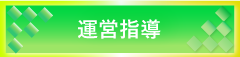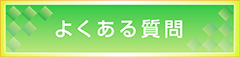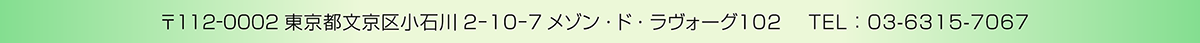■就労継続支援事業の新規指定及び指定・指導ガイドライン(案)について
こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、就労継続支援事業の新規指定及び指定・指導ガイドライン(案)について、お伝え致します。
10月20日、厚生労働省は、障害福祉サービスのうち、特に「就労継続支援(A型・B型)」事業所の新規指定及び既存運営状況の把握・指導 に関して、全国の自治体に向けた「指定・指導ガイドライン(案)」を示しました。
https://www.joint-kaigo.com/articles/41217/
このガイドライン案の目的は、支援サービスの質を全国レベルで底上げすること、形式的・形式通りの指定審査・指導から、実質的に中身を精査する「実質審査」へと転換を図ることにあります。
1.背景・必要性
現在、就労継続支援事業所の指定申請については、書類が整っていれば自治体が不受理にできないという運用があり、「指定を取れば良い」という形で参入する事業者も存在すると指摘されています。
また、自治体ごとの審査・指導担当職員の能力差や運用のばらつきが、支援の質確保を困難にしており、就労能力向上に実質的に寄与しない事業所が散見されるという課題もあります。
こうした背景から、ガイドライン案では、①指定・指導のプロセスを明確化し、②自治体がチェックすべき観点を整理し、③標準的なチェックシート(生産活動シート)等の提出も想定し、統一的で実効性のある審査・指導を促すものとなっています。
2.主な内容・ポイント
(1)新規指定に関する観点
・指定を行う権限を持つ自治体(指定権者)は、申請を受ける前段階から、指定希望者(法人・事業所)に対して事前説明及び確認を行うことが望ましいとしています:例えば、支援制度・指定基準・就労支援事業会計等の知識の有無、サービス提供方針、生産活動の見込み収入など。
・事業計画書・収支予算書・生産活動内容などを審査する際、地域のニーズ把握・サービス選択理由・利用者募集の方法・収入見込み・職員配置・研修計画などを丁寧に確認すること。申請書類の流用は原則認めず、実態に即した記述がされているかを重視しています。
・生産活動については、ただ「居場所を提供する」「作業をしている」というだけではなく、一般就労に必要な知識・能力の向上に資する内容であるか、安定的な収益が確保できる見込みがあるか、地域の就労機会等との関連性があるか、といった観点での確認が示されています。
・利用者募集の際に不適切な誘因(例:高額な提示、商品券配布、交通費・昼食費の不当な謳い文句)などがあれば指定基準違反の可能性ありとの注意も明記されています。
(2)既存事業所の運営状況の把握・指導
・指定後運営中の事業所についても、指定権者は「管理者業務・人員配置」「生産活動の実態・収支状況」「利用者支援内容の実施状況」「賃金・工賃の支払い状況」「会計情報」「施設外就労の実態」など幅広い観点から点検を行う必要があります。
・定期的・継続的なモニタリングを通じて、サービスの質が維持されているか、適切な運営がされているかを確認する仕組みを構築するよう促しています。審議会でも「専門機関との連携」「障害種別(視覚・聴覚等)ごとの対応力」「職員処遇の水準」等をチェック項目に加えるべきという意見が出ています。
3.今後の対応・影響
厚労省は、このガイドライン案を自治体に対して早期に通知し、今後はこの案に沿った運用を全国的に求めていく方針です。
このため、就労継続支援サービスを運営又は参入を検討している事業者・法人にとっては、これまで以上に「中身を伴った事業計画・運営体制・支援内容・生産活動収益性」等を整理しておく必要があります。特に、収益見込みが曖昧、生産活動が実質的な就労能力向上に直結しない、利用者募集手法が安易・誘因的といった運営では、指定取得・継続において厳しいチェックを受ける可能性がありますので、留意しましょう。
特に今後は就労会計基準の知識をきちんと持って運営できることがとても大切になりますので、顧問の税理士さんなどと相談をしながら、就労会計基準に基づいた明細書や計算書が作成できるよう、準備を進めていきましょう。
以上、参考になりましたら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。
就労継続支援事業の新規指定及び指定・指導ガイドライン(案)について