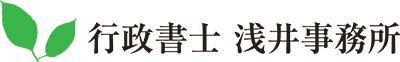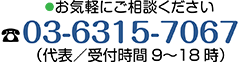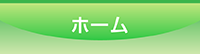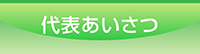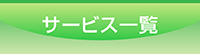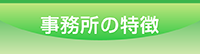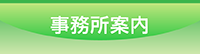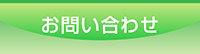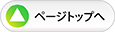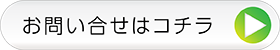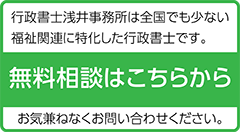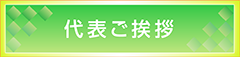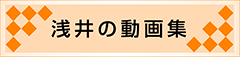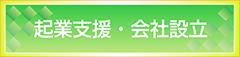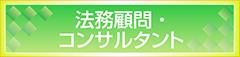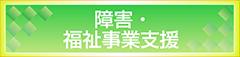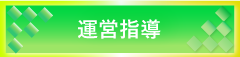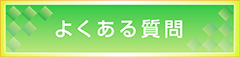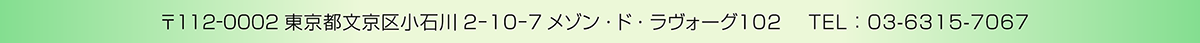ブログ更新しました。

■障害福祉サービス事業所様に置いて取組みが必要な4月からの加算、処遇改善、賃上げ補助金やその他について
こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
本日は障害福祉サービス事業所様に置いて取組みが必要な4月からの加算、処遇改善、賃上げ補助金やその他についてご案内いたします。
1.4月からの加算の体制届、処遇改善計画書について
毎年4月からの加算体制届、処遇改善計画書の提出は4月中旬頃の提出期限となりますが、指定権者からのご案内や様式の公表が提出期限間近になってから公表される傾向にあります。
そのため、それから準備をすると申請に間に合わなくなる可能性があるため、お手数ですが現時点から準備をされることをお勧めいたします。
・昨年度の加算体制届や処遇改善計画書をご確認いただき、4月以降に取れる加算について前年度の集計が必要なものは集計など行ったうえで、どの加算をとるのか、区分に変更がないか、減算になるものなどはないのか等前年度の様式で素案作り進めることをお勧め致します。
・処遇改善計画書も前年度の内容を参考に、前年度の国保連からの支給金額を集計し、どれぐらいの平均売上になるかの算定や前年度の賃金総額などの入力欄があるので、こちらも集計をしておき、計画書の内容に変更がないか、職場環境要件など取り組み内容に変更がないか等こちらも前年度の計画書を使用して、今年度の計画書の素案作りを進めることをお勧め致します。
以下本年度の報酬改定についての厚生労働省資料もお送りします。
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html
2.処遇改善については上記をふまえて集計をしておいたら、7月に実績報告書の提出が必要となりますので、前年度にもらった処遇改善加算額の集計、今年度改善をした賃金が以前額などの集計も進めておき、改善額が加算額を上回っているのかの確認も進めておくことをお勧め致します。
3.賃上げ、処遇改善緊急支援事業補助金について
処遇改善と別枠で賃上げを行うための補助金です。
以下簡易版としてまとめました。
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:651f7d09-2f12-4836-8269-87a97326e094
処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定できていれば、令和7年12月の国保連からの支給金額の入力と、要件としては460万円以上の年給与総額の従業員の配置かその誓約、職場環境要件の
入力ができれば補助金を受けることができますので、職場環境要件としてどの項目を選ぶか等ご準備を進めることをお勧め致します。
4.GビズIDについて
GビズIDは、デジタル庁が運用する法人・個人事業主向けの共通認証システムです。
1つのIDで複数の行政手続きにログインできる仕組みです。
主な利用先
・補助金申請
・許認可申請、変更届等
・電子申請システム(e-Gov等)
今後は「GビズIDでログインして提出」が主流になる可能性はかなり高いです。
介護保険事業などではすでにGビズIDからの申請に切り替わってきております。
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:5127927a-a31e-46c7-b56e-9a57e19f36b2
また、以下「こども性暴力防止法」が今年の12月から施行されますが、こどもをお預かりする学校や児童通所事業所(放デイ等)は4月までにGビズIDの取得を求めております。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
上記の理由により、GビズIDをまだ取得されていない法人様においては、取得をお願いします。
※こちらは当事務所の今後の業務のお話になるのですが、今後は上記の通り、GビズIDを使用し、法人様から簡単にいろいろなことが申請できる方向に進んでいきます。
そのため、当事務所では申請の代行業務ではなく、GビズIDなどの電子申請を法人様が活用し、補助金や申請を効率的に有効活用していくことを支援したり、法人様と一緒に考えていくことを今後の方針として考えております。
5.情報公表制度
情報公表が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60356.html
まだ取り組んでいない場合には、3月末までにワムネットからログインして申請を行いましょう。
経営状況の見える化は、直近の決算については3月末までに申請、4月以降は決算月から
3か月以内に毎年申請がワムネットから送信して申請が必要です。
こちらも必ず行うようにしましょう。
6.年間で取り組みが必要な委員会、研修、訓練等について
年間で取組必要な内容をまとめましたので、参考にして頂けたら幸いです。
取り組みが足らないと減算になる可能性もありますので、必ず取り組んでいただくようお願いします。
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:64bfd203-c824-498f-b14e-f64e5de7bb2e
以上、ご参考になりましたら幸いです。
最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今回の内容が少しでも事業所運営に役立ちましたら幸いです。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。